人手不足、賃上げ、生産性向上…その悩み、もう終わりにしませんか?最大1億円の「中小企業省力化投資補助金(一般型)」活用で、未来の工場・店舗を実現!(2025/7/31(木)締切)
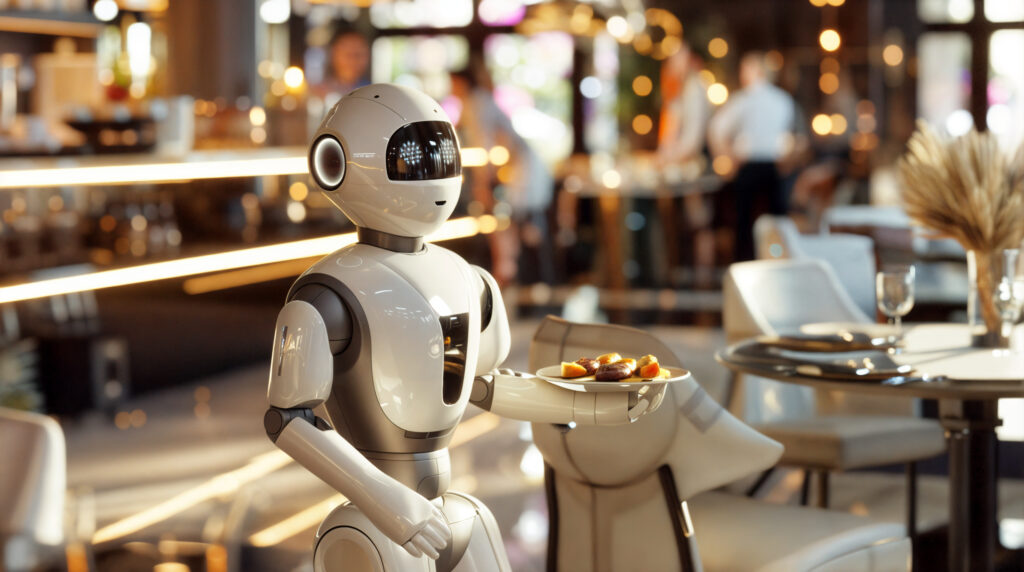
「人が足りない」「賃上げしたいけど、原資が…」「もっと効率的に生産性を上げたい」——。
多くの中小企業の経営者様が、日々このような課題に直面しているのではないでしょうか。
デジタル技術の進化が目覚ましい現代において、これらの課題を解決する鍵は、IoTやロボットなどの「省力化設備」の導入にあります。
しかし、「導入費用が高額でなかなか踏み切れない…」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。
そこで今回ご紹介したいのが、人手不足に悩む中小企業を力強く後押しする「中小企業省力化投資補助金(一般型)」です!
この補助金は、最新のデジタル技術を活用した専用設備導入費用の一部を国が補助することで、皆さまの生産性向上と賃上げを強力に促進することを目的としています。
締め切りは、2025年7月31日(木)と迫っています。ぜひこの記事を読み進め、あなたの企業がこの補助金を活用できるかどうか、そしてそのメリットを最大限に引き出す方法をご確認ください。
中小企業省力化投資補助金(一般型)
本補助金は人手不足に悩む中小企業がIoTやロボットなどのデジタル技術を活用した専用設備を導入する費用の一部を補助することで、生産性向上と賃上げを促進することを目的としています。
【補助額・補助率】
従業員数に応じた補助上限額が設定されています。
- 5人以下:750万円(特例適用時1,000万円)
- 6~20人:1,500万円(特例適用時2,000万円)
- 21~50人:3,000万円(特例適用時4,000万円)
- 51~100人:5,000万円(特例適用時6,500万円)
- 101人以上:8,000万円(特例適用時1億円)
特例措置とは
以下の大幅賃上げを行う事業者に対し、補助上限額が50~2,000万円上乗せされます。
- 給与支給総額の年平均成長率+6.0%以上増加
- 事業所内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+50円以上の水準
補助率は以下の通りです。
- 中小企業:補助金額が1,500万円まで1/2(特例適用時2/3)、1,500万円を超える部分1/3。ただし最低賃金引き上げに係る特例適用の中小企業は、補助金額1,500万円まで2/3、1,500万円を超える部分1/3に引き上げられます。
- 小規模企業者・小規模事業者、再生事業者:補助金額が1,500万円まで2/3、1,500万円を超える部分1/3。
本補助金は設備投資を促進する性質から、機械装置・システム構築費以外の経費については、補助上限額が総額で500万円(税抜き)までとなります。
【対象者】
中小企業、個人事業主、NPO法人、社会福祉法人等が対象になります。
- 日本国内に本社及び補助事業の実施場所を有している必要があります。
- 中小企業の場合、業種ごとに資本金、常勤従業員数の上限が定められています。
- 常勤従業員数は、労働基準法第20条に基づく「あらかじめ解雇の予告を必要とする者」と解されます。
【対象となる事業】
本事業は、中小企業等の売上拡大や生産性向上を後押しするため、人手不足に悩む中小企業等がIoT・ロボット等のデジタル技術を活用した専用設備(オーダーメイド設備)を導入するための事業費の一部を補助することで、省力化投資を促進し、付加価値額や生産性向上を図るとともに、賃上げにつなげることを目的としています。
以下の基本要件を全て満たす3~5年の事業計画を策定する必要があります。
- 労働生産性の年平均成長率+4.0%以上増加。
- 給与支給総額の年平均成長率+2.0%以上、又は1人当たり給与支給総額が事業実施都道府県における最低賃金の直近5年間の年平均成長率以上増加。
- 事業場内最低賃金が事業実施都道府県における最低賃金+30円以上の水準であること(最低賃金引き上げ特例適用事業者を除く)。
- 従業員21名以上の場合、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を「両立支援のひろば」に公表等していること。
その他、以下の要件を満たす必要があります。
- 省力化指数(設備導入により削減される業務に要する時間の削減割合)を計算した事業計画の策定。
- 事業計画上の投資回収期間を根拠資料とともに提出。
- 3~5年の事業計画期間内に、設備投資前と比較して付加価値額が増加する事業計画の策定。
- 人手不足解消に向けたオーダーメイド設備等の導入
- (汎用設備でも、導入環境に応じたカスタマイズや複数組み合わせによる高い効果が見込まれる場合は対象)。
- 外部SIerを活用する場合、3~5年の事業計画期間内における保守・メンテナンス契約を締結し、SIerは必要な体制を整備すること。
- 金融機関からの資金調達を予定している場合、金融機関による事業計画の確認を受け、確認書を提出すること。
補助事業の実施場所を特定していることが必須で、応募時点で建設中や土地のみ確保している場合は対象外です。
【応募スケジュール・応募方法】
今回は第3回公募となり、2025年8月上旬より申請受付が開始される予定です。締切は2025年8月下旬で、採択発表日は2025年11月下旬(予定)となっています。
本事業の申請は、電子申請システムのみで受け付けます。申請には「GビズIDプライムアカウント」の取得が必須であり、取得には一定期間を要するため、早めの手続きが推奨されます。
補助事業実施期間は交付決定日から18か月以内(採択発表日から20か月後の日まで)です。この期間内に契約、納品、検収、支払い等の全ての手続きを完了し、実績報告書を提出しなければなりません。
【応募書類】
主な提出書類は以下の通りです。
- 全事業者共通:損益計算書・貸借対照表(直近2期分)、事業計画書(参考様式その1・その2、指定様式その3)。
- 法人の場合:履歴事項全部証明書(発行から3か月以内)、納税証明書(その2、直近3期分)、法人事業概況説明書、役員名簿、株主・出資者名簿。
- 個人の場合:確定申告書の控え(第一表)、納税証明書(その2、直近1年分)、所得税青色申告決算書または所得税白色申告収支内訳書。
その他、事業実施場所が複数ある場合、最低賃金引き上げ特例を適用する場合、他の助成制度の利用実績がある場合、金融機関から借り入れを受ける場合、事業承継またはM&Aを実施した場合の書類、導入予定の機器装置についてのカタログや説明資料などが必要に応じて求められます。
事業計画の作成を外部の支援を受けた場合は、申請画面の「事業計画書作成支援者名」「作成支援報酬額」の欄に当該事業者名、報酬の内容(成功報酬の場合は採択時の金額)、契約期間等を必ず記載してください。
記載がないことが判明した場合は、虚偽申請として不採択、採択決定の取消、補助金の返還、不正内容の公表等が行われます。
【対象経費】
補助対象となる経費は、本事業の対象として明確に区分でき、必要性及び金額の妥当性を証拠書類によって確認できるものです。
交付決定を受けた日付以降に契約(発注)等を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものに限られます。
■必須経費
機械装置・システム構築費:単価50万円(税抜き)以上の設備投資が必須です。
専用の機械・装置、工具・器具(電子計算機、デジタル複合機等)の購入、製作、借用にかかる費用。
専用ソフトウェア・情報システムの購入・構築、借用にかかる費用。
上記と一体で行う改良または据付けにかかる費用。
システム構築費の場合、実績報告時に要件定義書や開発費用算出資料の提出が必要となることがあります。
リース利用の場合、対象リース会社との共同申請が可能で、リース料から補助金相当額が減額されることが条件となります。
導入したシステム等のサイバーセキュリティ対策のための市販パッケージのウイルス対策ソフト等の購入費用も対象です。
■任意経費(上限額あり)
運搬費:運搬料、宅配・郵送料等(購入時の機械装置の運搬料は機械装置費に含む)。
技術導入費:本事業に必要な知的財産権等の導入にかかる費用(上限:補助対象経費総額の1/3)。
知的財産権等関連経費:特許権等の取得にかかる弁理士手続き代行費用、関連経費(上限:補助対象経費総額の1/3)。
外注費:専用設備の設計等の一部を外注する場合の経費(上限:補助対象経費総額の1/2)。サイバーセキュリティ対策のための脆弱性診断費用も対象です。
専門家経費:技術指導や助言のために依頼した学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家へのコンサルティング業務や国内旅費等の費用(1日上限5万円、上限:補助対象経費総額の1/2)。
クラウドサービス利用費:専ら補助事業のために利用するクラウドサービスやWEBプラットフォームの利用費のみ。サーバーの領域を借りる費用、サーバー上のサービス利用費用等が対象です。
【対象外となる経費】
- 交付決定前に発生した経費(いかなる理由でも事前着手は認められません)。
- 既に導入されている既存システムやソフトウェアのバージョンアップ・アップデート費用・改修のみの事業。
- 開発を必要としないパッケージソフト・汎用ソフトウェアの購入および導入設定・セットアップ費用。
- 導入する設備とは関連のない設置作業や運搬費、データ作成費用やデータ投入費用等。
- 自社事業の省力化が目的ではなく、販売することを目的とした、製品・サービス等の開発・調達に係る経費。
- 社内システム・自社の基幹システム等の開発・改修を自社の人員で実施する場合の人件費。
- 工場建屋、構築物、簡易建物等の取得費用や、設置場所の整備工事、基礎工事にかかる費用。
- 事務所等の家賃、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費、電話代、インターネット利用料金等の通信費(クラウドサービス利用費に含まれる付帯経費を除く)。
- 商品券等の金券、文房具などの事務用品等の消耗品代、飲食、奢侈、娯楽、接待等の費用。
- 不動産の購入費、自動車等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用。
- 税務申告、決算書作成等のための税理士、公認会計士等に支払う費用及び訴訟等のための弁護士費用。
- 公租公課(消費税等)。
- 汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費(例:事務用のパソコン・プリンタ・文書作成ソフトウェア・スマートフォン・タブレット端末・カメラ・家具)。
- 中古品購入費。
- 同一代表者・役員が含まれている事業者、みなし同一法人内の事業者(親会社・子会社間など)、資本関係がある事業者への支払。
- 同一企業の部署間の支払(機械装置等の社内発注、社内製造も含む)。
- 対象リース会社が中小企業等とリース契約を結ぶ際に発生する金利や保険料。
【審査基準について】
提出された事業者情報、事業計画書に基づき、事務局が内容の審査を行います。
書面審査では、以下の観点で評価されます。
- 補助対象事業としての適格性:公募要領に記載の対象事業、対象者、申請要件、補助率等を満たしているか。
- 技術面:省力化指数、投資回収期間、付加価値額、オーダーメイド設備の4つの観点。省力化指数が高く、投資回収期間が短い、付加価値額の年平均成長率が大きい、オーダーメイド設備(または汎用設備でも高い省力化効果や付加価値を生み出す組み合わせ)の導入が示されているか。
- 計画面:スケジュールが具体的か、企業の収益性、生産性、賃金が向上するか。補助事業遂行能力、資金調達の見込み、成果の優位性・収益性、高い賃上げ目標の実現可能性、会社全体へのシナジー効果(省力化された労働力を高付加価値業務に振り向ける等)が評価されます。
- 政策面:地域経済への貢献、イノベーション牽引、社会課題解決への寄与。地域未来牽引企業、地域未来投資促進法に基づく計画、アトツギ甲子園出場者、革新的で優れた省力化技術を持つ中小事業者の製品(イノベーション製品)の導入などが考慮されます。
加点について
特定の取組を行う事業者には加点が行われます。
- 過去3年以内の事業承継またはM&A。
- 事業継続力強化計画/連携事業継続力強化計画の認定取得。
- 「成長加速マッチングサービス」への登録。
- 賃上げ加点(給与支給総額の年平均成長率4.0%以上増加、事業場内最低賃金が毎年最低賃金より+40円以上)。
- えるぼし認定、くるみん認定。
申請書の審査には口頭審査が含まれます。口頭審査は、一定の基準で事業者を選定し、必要に応じてオンライン(Zoom等)で実施されます。
事業計画の適格性、優位性、実現可能性、革新性等が審査されます。審査は申請事業者自身(法人代表者等)1名が対応し、事業計画書作成支援者や経営コンサルタント等の同席は一切認められません。
【注意点】
補助金で取得する資産には、財産処分(売却、転用、破棄等)に制限が課されます。
事業計画期間終了時点において、給与支給総額または1人当たり給与支給総額の目標が未達の場合、達成率に応じて補助金の返還を求められます。
中小企業省力化投資補助事業(カタログ注文型)の製品カタログを事前に確認することが推奨されています。カタログ注文型は本事業と比べて申請が迅速かつ簡易です。
一般型は審査項目が多く、個別課題への対応や革新性が総合的に審査されます。
設備投資したい物が決まっている事業者様にとって、使い勝手が良い補助金です。弊所では補助金のサポートを行っていますので、共に計画を練り、申請締切までに申請できるよう準備を進めていきましょう。お気軽にお問い合わせください。
参考:補助対象となる業種、資本金、従業員数の表
| 業種 | 資本金 | 常勤従業員数 |
| 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 |
| サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 |
| ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 |
| ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 |
